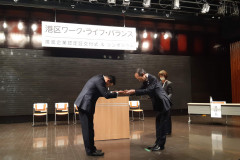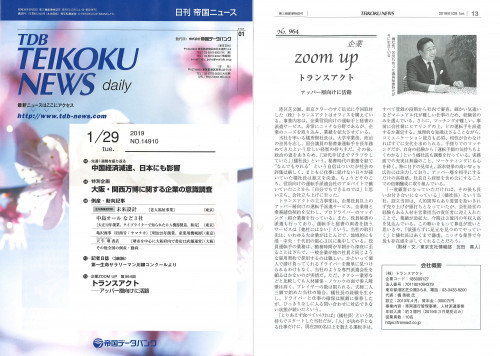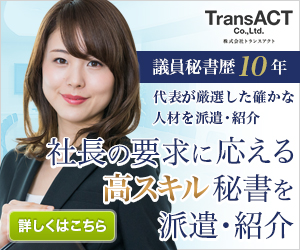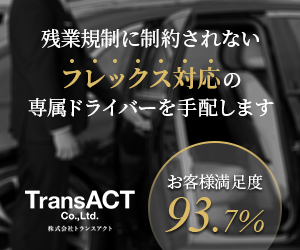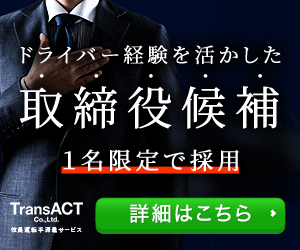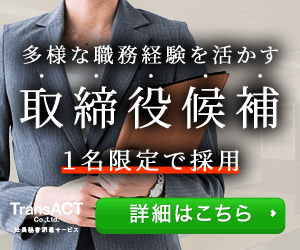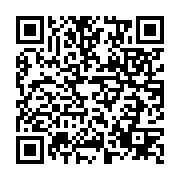NEWS
■第2回 無担保社債(私募債)発行のお知らせ

株式会社トランスアクトは令和5年1月31日、第2回 無担保社債(私募債「株式会社三菱UFJ銀行・東京信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付」)総額3千万円を発行いたしましたのでお知らせいたします。
株式会社トランスアクト(代表取締役社長 橘 秀樹) 第2回 無担保社債
(1) 発行金額:30,000,000円
(2) 発 行 日 :2023年1月31日
(3) 償 還 日 :2028年1月31日
(4) 償還期間:5年
(5) 発行代理人:株式会社三菱UFJ銀行
【証券保管振替機構】銘柄公示情報(一般債)
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第87条に基づく一般債の内容の公示
無担保社債(私募債)の発行に際しましては、財務内容、収益性について厳しい審査基準を満たす事が必要であり、今回の発行により弊社の成長性及び健全性に対して優良企業としての評価がなされたものと認識しております。
また弊社は本資金を、
①お客様満足度向上の為の投資
②人材育成と教育支援への投資
③新しい生活様式に対応する業務環境への投資
に重点的に活用して参りたいと考えております。
弊社は対外的に期待される信用と健全な財務体質を生かし、今後も更なる業容拡充に向けて邁進して参ります。
■<2月コラム>社長の仕事とは究極のところ何なのか?すべき仕事としてはいけない仕事

社長の仕事とは、ずばり「社長にしかできない仕事」です。しかし、それは一体何なのでしょうか。社長として自分がすべきことを知っておくことで、部下に任せる仕事も決めやすくなります。この記事では、社長としての役割や仕事を明確にしたい経営者に向けて、社長がすべき仕事や果たすべき役割について具体的に説明します。
1.社長は「指揮者」としての役割を果たす
ピーター・ドラッカーは、トップの仕事を「オペラの指揮者」と表現しています。オペラの指揮者は、オーケストラや歌手、裏方など、多種多様なメンバーを楽譜で率いて、最高の結果を出さなければなりません。会社もさまざまな役割を担う人がいて成り立つものであり、大事なのはチームワークです。指揮者として率先してチームをまとめ、アウトプットを最大化することこそが社長が取り組むべき仕事です。全体最適に配慮し、ヒト・モノ・カネなどの経営資源をバランスよく配置することに主眼を置きましょう。社長は会社に関わっている社員や家族の人生を背負っており、その責任は重大です。
2.具体的な仕事:会社の行き先を決める
社長は会社をまとめ、さらに行き先についても決める必要があります。別の言い方をすると、今後会社がどんな道を目指すのかという方向性を決められるのは社長だけです。具体的には、会社の経営理念や経営方針、将来的なビジョンなどを掲げ、社内外に共有しましょう。組織の大枠を決定したら、その維持に必要な人材配置や社内制度の整備などを行います。大事なのは、自分ひとりで動くのではなく、他の経営陣や現場を率いる中間管理職などとも円滑なコミュニケーションを取り、協力してもらうことです。会社が目指す道がきちんと共有されていれば、部下も一丸となって社長に貢献してくれるでしょう。
3.具体的な仕事:お金の把握と資金繰り
夢ばかり語っていても会社は維持できません。必要な資金を調達して適切に配分し、社内のマネーフローを管理・把握することも社長の大事な役割です。マネーフローが詰まってしまうと、会社は事業を維持できず倒産してしまいます。資金が足りない場合は、社長が中心となって事業計画や返済計画を立て、銀行からお金を借りなければなりません。また、資金調達の合理性について、株主から説明を求められる場合もあります。厳しいコスト意識を持ち、無駄遣いがないか定期的にチェックすることも大切です。
4.具体的な仕事:人を育てる
社員は会社の大事な資産であり、人材育成も社長の大事な仕事です。ただし、新入社員の人材育成にまで口を出していたら、時間がいくらあっても足りません。人材育成において、社長がすべきことは、人材育成の方向性や予算決めなどです。会社が将来的に成長していくために、どんな人材が必要かを明確にしておきましょう。さらに、公平な人事評価制度も社員のモチベーション維持には必要です。正しい判断を行うためにも、現場の中間管理職などを通じて、部署ごとの内情も把握しておかなければなりません。社長に近い立場の管理職は、社長自らが育成する必要があります。自分の後継者を育てるのも大切な仕事です。
5.してはいけない仕事は「作業」
最後に、社長がしてはいけない仕事は「作業」です。現場の状況や課題を把握することは大事ですが、社長自らが現場の最前線に立つ必要はありません。社長としてやるべき仕事はいくらでもあります。得意だからといってつい作業をしてしまい、肝心の判断・決定作業がおろそかになっては本末転倒です。また、社長が現場にいることで、ほかの社員が指示待ちになり、かえって全体のアウトプットが落ちてしまう恐れもあります。現場に課題がある場合は、あくまで解決案を提示するだけにして、作業は現場の社員に任せましょう。
社長にしかできない仕事に集中すべき
社長としてすべき仕事や役割は山のようにあります。1日に使える時間は限られていますので、本当に必要な仕事とそうでない仕事とを区別し、取捨選択することが大切です。忙しくて時間が足りない場合は、運転手や秘書を雇って、作業の時間を減らしてみてはいかがでしょうか。捻出できた時間で、本来すべき仕事を推進していきましょう。
社長・経営者に関する「トランスアクトグループ」の記事も読まれています
社長・経営者に関する「一般財団法人トランスアクト財団」の記事も読まれています
社長・経営者に関する「株式会社トランスアクトホールディングス」の記事も読まれています
役員運転手・社長秘書に関する「株式会社トランスアクト」の記事も読まれています
役員運転手・運転手・ドライバーに関する「DRIVE4ME」の記事も読まれています
社長秘書・秘書・セクレタリーに関する「SECRETARY4ME」の記事も読まれています
■港区ワーク・ライフ・バランス推進企業として認定されました

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業として株式会社トランスアクトが新規認定され、武井雅昭港区長より認定証の交付を受けました。
ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいる港区内の事業者またはこれから取り組みを進めたいと考えている経営者・管理職・担当者又はこの取り組みに興味のある方が対象で、港区では、仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやすい職場の実現に向けてワーク・ライフ・バランスの取組を推進している中小企業を認定し、その取組を応援しています。
■第1回 無担保社債(私募債)発行のお知らせ

トランスアクトグループ企業の株式会社トランスアクトは令和2年12月30日、第1回 無担保社債(私募債「株式会社みずほ銀行・東京信用保証協会共同保証付」)総額3千万円を発行いたしましたのでお知らせいたします。
株式会社トランスアクト(代表取締役 橘 秀樹) 第1回 無担保社債
(1) 発行金額:30,000,000円
(2) 発 行 日 :2020年12月30日
(3) 償 還 日 :2025年12月30日
(4) 償還期間:5年
(5) 発行代理人:株式会社みずほ銀行
【証券保管振替機構】銘柄公示情報(一般債)
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第87条に基づく一般債の内容の公示
無担保社債(私募債)の発行に際しましては、財務内容、収益性について厳しい審査基準を満たす事が必要であり、今回の発行により弊社の成長性及び健全性に対して優良企業としての評価がなされたものと認識しております。
また弊社は本資金を、
①お客様満足度向上の為の投資
②人材育成と教育支援への投資
③新しい生活様式に対応する業務環境への投資
に重点的に活用して参りたいと考えております。
弊社は対外的に期待される信用と健全な財務体質を生かし、今後も更なる業容拡充に向けて邁進して参ります。